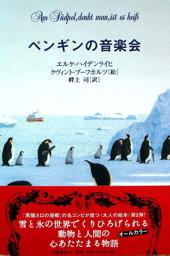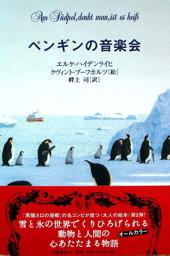生まれついての激しい気性と同胞愛の深さ、カリスマ性によって、生後六週間でドン・ネロ・コルレオーネの名を定着させた稀代の黒猫。イタリアの農村に生まれたそのネロが、ある家に引き取られてドイツに移住し、晩年になってイタリアの故郷に戻ってくるまでを、周囲の動物や人間達との関係の中で描く、スケールの大きな絵本。主人公がネコ達でなければ、それこそコルレオーネの名が示す通り、『ゴッドファーザー』のような一大叙事詩とも読めそうな物語ですが、動物や人間達のユーモラスな描写や、本全体の短さによって、むしろ“ミニ叙事詩”とでも呼びたくなる愛らしい作品になっています。しかし、老いたネロが故郷に帰ってきてからの、どこがどうというのではないけれど、不思議に胸が切なくなるような、哀愁を帯びたリリシズムは、この本に、単なる動物絵本以上の魅力を加えていると言えるでしょう。 |